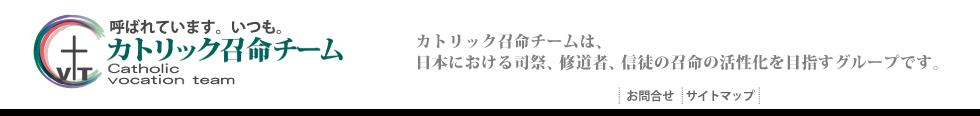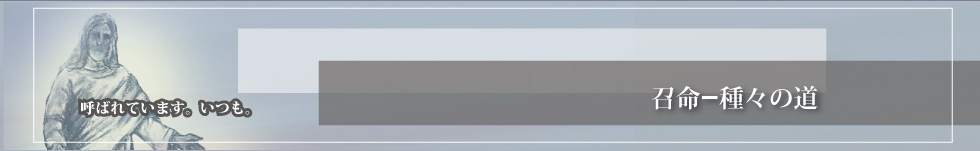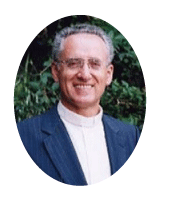 司祭の特別召命をいただいた者として、神が人を呼び、人間は神に応えていくといういわゆる召命の問題に対して、若いときからわたしは大きな関心をいだいてまいりました。 司祭の特別召命をいただいた者として、神が人を呼び、人間は神に応えていくといういわゆる召命の問題に対して、若いときからわたしは大きな関心をいだいてまいりました。
1960年代に行われた公会議まで、”神の招き”ということばが流行していました。旧約時代の預言者、新約時代の使徒とその後継者・・・・いつの時代においても、教会の中で一つの使命を果たすため、神に選ばれた人々が大勢いたと言えます。ところが、公会議がもたらしたあたらしい風や、その後起こった特別召命の急激減少がきっかけとなって、「召命」というとき、神の呼びかけだけでなく、人間がどういう心の姿勢で応えていくかが重要なポイントとなりました。そしてその結果、召命の問題に対する人間科学的な研究が営まれ、召命神学のほかに、召命心理学、召命社会学、召命教育学その他の学際的なアプローチから、召命学という学問が確立しました。
興味深いことに、80年代、90年代の召命に関する論文、記事、また書簡にも、心理学的な内容が多く見られましたが、最近は以前より少なくなりました。かわりに、現代召命学では、神のみ心とその恵みと同様、人間の自由意志やその人の適性、努力、人格などの要素も重要であるという均衡のとれた見方が一般的なものとなりました。いみじくも、わたしの論文指導教授が繰り返して教えてくれたように、「召命は神の恵みと人間の自由の神秘だ」ということではないでしょうか。
さて、神様は教会に必ず十分な司祭や奉献者を与えてくださると信じながらも、司祭の数は減少し、大きくなる数字と言えば、その平均年齢を表す数字だけです。そこで特に地域教会はこの問題を重要な問題として受け止め、意識、祈り、研究、行事その他でもって動かなければならないと思います。
具体的に、召命促進とつながり、参考となるようなヒントを下記に述べてみます。
1 教会で、特に若者と話すとき、人生がすばらしいおくりものであり役割であること、またその役割を発見しそれを精一杯果たすことは人間の道であること、そして人生は深い意味を持つものであり、その追求こそ幸福への道であることを知らせること。
2 人生は他者に開かれるためであり、特に最高の他者である神に開かれていることが人生の優先課題であると示すこと。
3 倫理観を持ち、人との連帯性を大事にしながら、自分の人生の計画を進めなければならないことを教えること。
4 司祭としてキリストに従って行き、言葉、行い、祈りを通して、人々に主の福音を述べ伝え、人々の霊魂の救いのために命をかける人生より喜ばしい人生はないことを示す司祭や奉献者が、若者と接触すること。 微笑みでもって、司祭になってよかったと示してくれる司祭こそ、召命の芽生えの一番のきっかけとなります。
このような働きかけにより、教会や家庭において、いわゆる “ Vocation culture ”(召命の雰囲気)が生まれ、自然に、若者はキリストに従って行く意味と生きがいを感じられるようになるでしょう。
なお、国によって、また修道会によって、召命促進のためにさまざまな取り組みが行われていますが、日本では“カトリック召命チーム”があります。
http://c-v-team.com
このカトリック召命チームは、池長潤大司教様および野村純一司教様のご指導のもとに、日本における司祭、修道者、信徒の召命の活性化を目指すグループです。
いずれにしても、召命は神秘です。 神様が絶えず人の心に呼びかけておられますが、呼ばれた人が選ばれた人となるように、私たちが強く希望し、熱心に祈り、自分なりに何らかの形で貢献すれば、必ず新しい召命の花が咲くにちがいないと思います。 |